炭素の同素体
黒鉛とダイヤモンドが同じものからできていると聞けば驚くものです.
一方は黒色の導電体で、もう一方は透明の絶縁体と、見た目も特性も何もかも違いますが、同じように炭素から構成されています.このように同じ元素からできているにも関わらず、異なる見た目や性質を示すものを同素体と呼びます.
様々な元素において同素体が報告されていますが、とりわけ炭素では多くの同素体が知られています.
炭素は周期表の14族に属し、地球上に豊富で安価な元素であると同時に、多種多様な化学結合を示すことでも有名です.有機化合物を例に挙げるまでもなく炭素を含んだ化合物は数多いのですが、黒鉛とダイヤモンド以外の同素体が見つかったのは20世紀後半になってのことです.
1985年のフラーレンの発見を皮切りに、カーボンナノチューブ、グラフェン、そして最近ではこれらの構造を組み合わせたような新たな同素体が報告されています.炭素と炭素の間の結合は非常に強いため軽く頑丈な構造材料として活用されたり、炭素の特殊な電子状態を活かしてエレクトロニクスや量子デバイスとしての応用も盛んです.
今回は、同素体の中でも炭素に着目していきます.
炭素・炭素結合と同素体
メタンなどの有機化合物の構造を考えれば分かるように、炭素は隣接する4つの原子と結合していることが多いです.炭素原子の2s軌道に2つ、2p軌道に2つの合計4つの価電子を持ちますが、これらは混成によって互いに等価な軌道を形成し、隣の原子と共有結合します.
ダイヤモンドでは炭素原子が隣り合う4つの炭素原子とそれぞれ共有結合していますが、このとき電子はsp3混成軌道にあります.すなわち、s軌道と3つのp軌道が混成することで互いに等価な4つの軌道を形成し、四面体中心にある炭素原子が頂点の方向に手を伸ばすことで結合を形成します.
一方、グラファイトでは、炭素原子はそれぞれ3つの炭素原子としか結合を形成していません.このとき炭素原子はsp2混成軌道を形成しており、s軌道と2つのp軌道が混成することで3つの等価な結合を作っています.正三角形の中心にある炭素原子が頂点方向に手を伸ばして結合し、残された1つの電子は正三角形と垂直な方向に伸びて結合には関与せず残ります.
もう一つの混成のパターンとしてsp混成軌道も知られていますが同素体においてはほとんど見られません.以下では、具体的な炭素の同素体を見ていきます.
ダイヤモンド
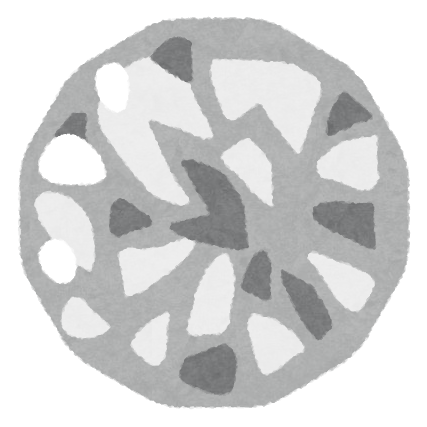
ダイヤモンドは太古から知られる炭素同素体で、宝飾品としてあまりにも有名です.透明でキラキラしているだけでなく、その顕著な特性から産業的にも重要な物質です.あらゆる天然資源の中で最も硬いことから切削材料に使用されるほか、非常に大きな熱伝導率を活かして放熱剤としても利用されます.
さらに、ダイヤモンドは半導体としての応用先も見つかっています.絶縁体のダイヤモンドが半導体?と首を傾げますが、不純物の添加によってp型とn型の材料とすることができます.その大きなバンドギャップを活用して、ワイドギャップ半導体としてパワーエレクトロニクス分野での利用や紫外発光のダイオード材料としても有力です.
前述の通り、ダイヤモンドでは炭素原子同士が互いに4つの炭素原子と共有結合して堅牢な結晶構造を形作っています.この結晶構造をダイヤモンド構造と呼びます.sp3混成軌道にある電子は局在しており、ダイヤモンドが絶縁体であることと対応します.
ダイヤモンドについて詳しくは過去の記事を参照してください.
黒鉛(グラファイト)

ダイヤモンドよりも馴染みのある同素体が黒鉛(グラファイト)です.鉛と名前にありますが鉛は含まれていません.ダイヤモンドとは打って変わって柔らかく、素手でも容易にボロボロ崩れます.また、ダイヤモンドとは異なり電気をよく流す導電体です.
日常でよく見るのは、鉛筆の芯としての用途でしょう.これは黒鉛の柔らかさ(潤滑性)と黒色を活かしていますが、他にも黒鉛は単独あるいはオイルと併用しての潤滑剤用途で使用されます.また、導電性を活かして電極としての用途もあります.
黒鉛では炭素がsp2混成軌道を形成して互いに3つの炭素原子と結合しており、余った電子は面外方向に伸びています.このようにして形成されるハニカム上の炭素原子シートが何層も積層してできた物質が黒鉛です.
各シート同士はゆるく束縛されていることから剥がしやすく、これが黒鉛の柔らかさの由来です.また、結合に関与していない電子は隣の炭素原子へ移動することができるため、黒鉛は導電性を示します.
グラフェン

黒鉛は層状の物質であり、各層は容易に剥離できると述べましたが、これらはどこまで薄く剥がすことができるのでしょうか.究極の到達点が炭素1層のみから構成される原子シートであり、これをグラフェンと呼びます.
グラフェンは1991年に発見された物質です.黒鉛をテープで剥がし続ける操作を繰り返して得られたグラフェンは、驚きの性質を示しました.
まず、グラフェンにおける電子は非常に大きなキャリア移動度を示し、シリコンを優に超えます.これを活かし、グラフェンを用いた半導体集積回路への応用が検討されています.また、その特殊な電子構造に由来して量子ホール効果などの極めて特異な現象も見られます.その特異性から、グラフェンに関する研究によっていくつものノーベル賞が誕生しました.
グラフェンは黒鉛から剥離したして得られることから構造は黒鉛1層分と同じで、それぞれの炭素原子はsp2混成軌道を形成して3つの炭素原子と結合しています.黒鉛からの剥離のほか、基板上に炭素原子を成長させる方法でもグラフェンの合成が可能です.
グラフェンについて詳しくは過去の記事を参照してください.
フラーレン

フラーレンは、炭素原子が球状のクラスターとなった巨大な分子です.中でも最も小さく安定なのが炭素原子60個から構成されるであり、12個の五角形と20個の六角形からなるサッカーボール状の構造を示します.1985年に報告されたこの物質は建築家バックミンスター・フラーの名を冠してバックミンスターフラーレンと名付けられ、単に略してフラーレンと呼ばれるようになりました.
フラーレンの魅力は構造的な美しさだけでなく、その特異な性質にあります.sp2混成軌道を有する炭素原子によって構成されたフラーレンは、そのままでは物理的に安定で反応性を示しません.一方、化学反応は可能で、水溶性の官能基化を付加することで水溶性が増し、反応性を飛躍的に高めることができます.
例えば、ポルフィリンのような有機ドナー分子を結合させることで、光を化学エネルギーに変換可能な材料となります.フラーレンの外側だけでなく内側も魅力的であり、フラーレンの外部を化学反応によって切り開くことで内部に分子を挿入可能です.
だけではなく、
など炭素数のより多いフラーレン(高次フラーレン)も発見されています.報告当初はごく少量しか得られなかったフラーレンですが、現在ではトン単位で製造することが可能です.
カーボンナノチューブ

カーボンナノチューブは、その名の通り炭素からなるナノサイズの筒(チューブ)です.フラーレンがゼロ次元(点)、グラフェンが二次元(面)、ダイヤモンドが三次元(空間)であるとすれば、カーボンナノチューブは一次元の炭素同素体です.グラフェンを丸めて筒状にしたような構造をしており、1991年に報告されました.
sp2混成軌道を有する炭素原子によって構成されるカーボンナノチューブは、筒の太さに応じて伝導特性が変化します.この特性により、分子エレクトロニクス分野における半導体材料あるいは導電材料として応用研究が盛んです.
また、カーボンナノチューブは密度がアルミニウムの半分程度しか無いにも関わらず、強度が鋼の20倍もあり、銅の1000倍以上という高い電流密度耐性、銅よりも高熱伝導性を示します.このような最強クラスの材料特性を活かし、構造材料として特に有力視されています.
カーボンナノチューブはアーク放電法やレーザー蒸発法により合成されます.金属型と半導体型のチューブを作り分けることは困難ですが、種々の方法で分離してから利用されます.
その他の炭素の同素体
以上が炭素の代表的な同素体ですが、他にもいくつか例が知られています.
例えば、2023年には、グラフェンとフラーレンを組み合わせたような構造を持つ新しい同素体が合成され、graphullerene(グラフラーレン)と名付けられています.他に、理論的にはT-carbonやPenta-grapheneなどの様々な同素体が提唱されています.
まとめ
炭素ほど多くの化合物を形成する元素はありません.炭素化合物の豊富さは、炭素の結合様式の汎用性に基づくと考えています.
すなわち、まず4つの原子と共有結合が可能なことから結合先の組み合わせが膨大です.そして、炭素ー炭素結合が安定であることから無限にネットワークを広げることができます.さらに、状況に応じて混成軌道を形成することで結合数を減らしたり余った電子を受け入れることが可能なため、柔軟性も高いです.
これほどの汎用性を持つ炭素が地球上に豊富な資源であったことが、これほど生命や文明が発展した理由であると考えられます.
参考文献
化学と教育 2022 年 70 巻 9 号 p. 438-441
化学と教育 2011 年 59 巻 5 号 p. 258-259
Hirsch, Andreas. "The era of carbon allotropes." Nature materials 9.11 (2010): 868-871.
Sheng, Xian-Lei, et al. "T-carbon: a novel carbon allotrope." Physical review letters 106.15 (2011): 155703.
Zhang, Shunhong, et al. "Penta-graphene: A new carbon allotrope." Proceedings of the National Academy of Sciences 112.8 (2015): 2372-2377.
Meirzadeh, Elena, et al. "A few-layer covalent network of fullerenes." Nature 613.7942 (2023): 71-76.
Hou, Lingxiang, et al. "Synthesis of a monolayer fullerene network." Nature 606.7914 (2022): 507-510.